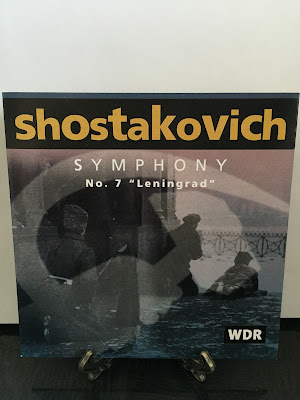中山七里著「おやすみラフマニノフ」を読んで

クラシック音楽とミステリーを絡めた小説でデビュー作である「さよならドビュッシー」そして「さよならドビュッシー 前奏曲」を以前読んでミステリーというよりはかなりライトなもので音楽小説という傾向が強いもので面白く読みました。 内容は音楽大学の厳重管理の保管庫から時価2億円のストラディヴァリウスのチェロが盗難に遭うという事件を発端に様々なことが起きていきます。 今回もデビュー作から登場している岬洋介という人物が探偵となり事件を解決に導きます。 ミステリーという面から読むとチェロ盗難のトリックはやや強引であったり、まとまりの無いオーケストラがしだいにまとまっていくくだりはマンガ「のだめカンタービレ」にダブったり、オーケストラのチューニングがヴァイオリンから始めるとか、オーケストラの金管・木管楽器の配置について首を傾げる描写などがあったりと雑念が入りますが、謎解きを楽しむというよりは登場人物の成長、所々で語られる言葉が印象に残ります。そしてなんといってもこの本はクラシック音楽を文章として読ませるということでは一番面白いです。 物語の最初に出てくるベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」の演奏シーン、パガニーニの「24のカプリース」や集中豪雨の中、避難所の体育館でチャイコフスキーにヴァイオリン協奏曲、物語のクライマックスで演奏されるラフマニノフのピアノ協奏曲第2番では音楽描写と登場人物の心情表現の両立が見事です。 難しい言い回しや複雑なテロップが無いぶん、文学としてみたもの足りないですが、クラシック音楽ファンなら音楽の演奏場面だけでも読んでみると良くきき込んでいる作品でも改めてきいてみたくなります。 作品のあちこちで語られる言葉には作者から読者へのメッセージが込められているようで、例えば56ページでは音楽家を目指す学生のアルバイト先であるとんかつ屋の親爺さんが音楽を職業とする難しさを述べる所は楽器を習わしている親子に、86ページでは就職活動を全敗した女子大生が愚痴るところは学生のみではなく正規雇用で働けない若者たちにも読ませてあげたいです。 331ページで出てくる「音楽は職業ではない。生き方なのだ」というくだりは七里さんがこの作品を通じて一番伝えたかった事のように思われ、この方は作風からはあまり感じられませんが熱い心の持ち主なのでしょうか?