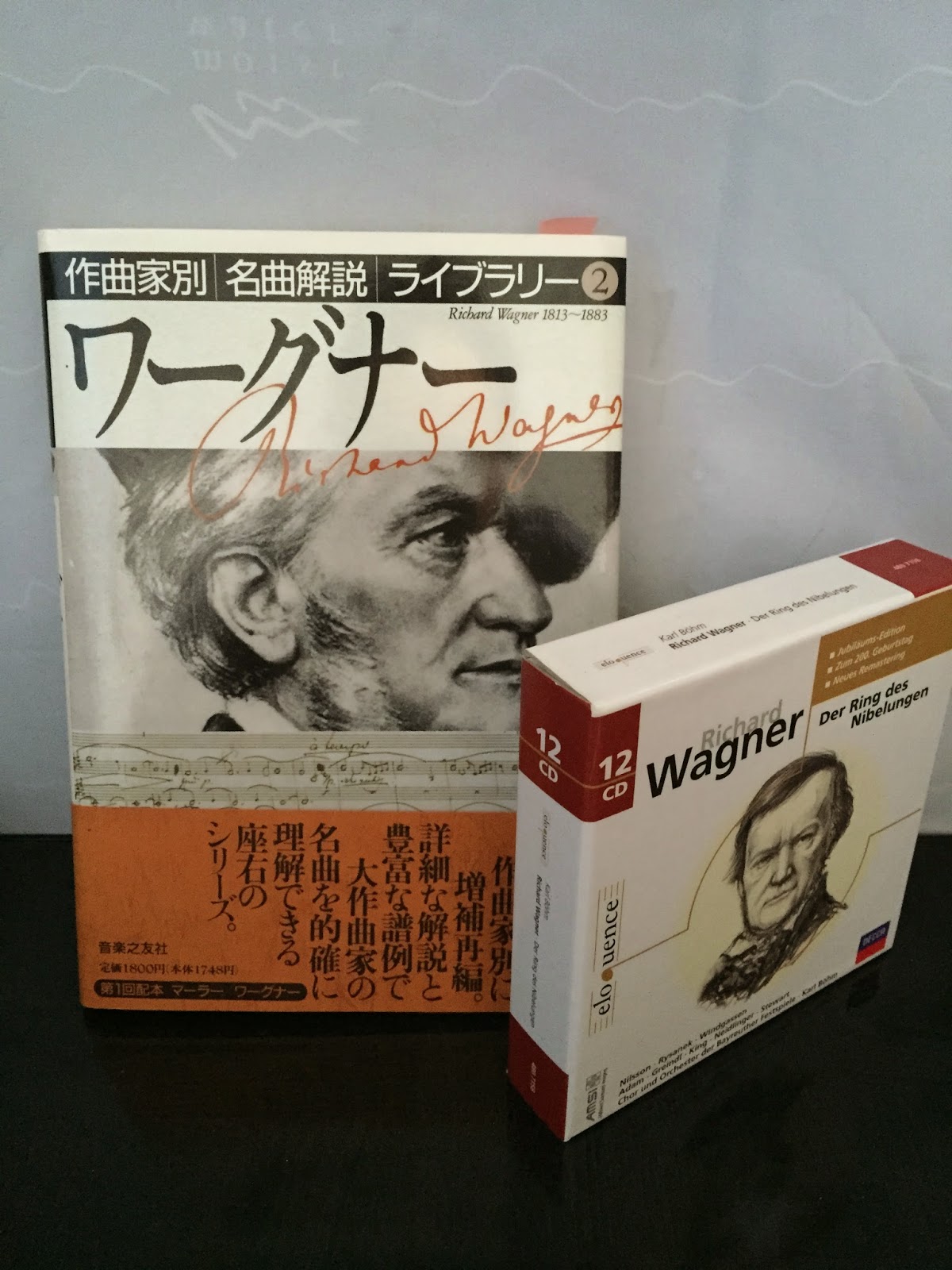今週の1曲(36)~ブラームス:哀悼の歌(悲歌)
今週ご紹介する作品はブラームスの合唱曲 「哀悼の歌」(悲歌)作品82 です。 友人でもある画家、ヘンリエッテ・ フォイエルバッハの死去に際してその追悼として1880年~1881年作曲され彼の母親に捧げられました。 シラーのギリシャ神話の「オルフェオの冥府下り」や美少年アドニス、トロイア戦争で死んだアキレスの母親の嘆きといった「死」に関するエピソードをベースに作られた詩が格調高く、フォイエルバッハの生涯は芸術家として不屈・不変のものとして描いているようです。 冒頭、 「Auch das Schone mus sterben (美しきものとして滅びねばならぬ!) Das Menschen und Gotter bezwinget (それこそが人々と神々の支配する掟)」 と歌われるカッコイイ詩と音楽に美しすぎて息をのみます! 終わりの 「 Auch ein Klagelied zu sein im Mund der Geliebten ist herrlich(愛する者の口より出ずる 嘆きの歌は素晴らしいものだ)」 を繰り返して曲を感動的に、しかも悲しみを乗り越えるように力強く、名残惜しげに曲を閉じていくところが崇高な感じで最高です。 題名が「哀悼の歌」とあり「死」を描いているのですが、美しくロマンティックな音楽に甘美さがあってブラームスはシブ~イというイメージですが、根っこのところはやっぱりロマン派の作曲家なんだなぁと実感する作品です。 《Disc》 もっぱらマーラー指揮者という印象の ジュゼッペ・シノーポリ が チェコ・フィルハーモニー管弦楽団、プラハ・フィルハーモニー合唱団 を指揮したディスクは繊細な表現が素晴らしいです。あと、FMできいた ティーレマン が ベルリン・フィル を振った演奏も力強さといった面ではとてもよかったと思いました。







.jpg)