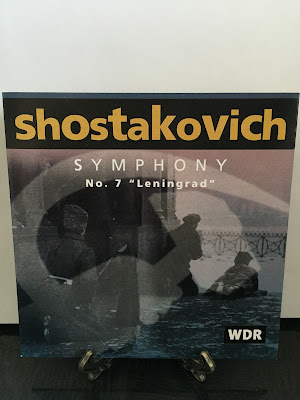松本交響楽団 第73回定期演奏会

新居への引越し&ネットを引かなかったので更新がご無沙汰になってました。 ザ・ハーモニーホール会館30周年演奏会として松本交響楽団をきいてきました。 プログラム ・ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 ・ベートーヴェン 交響曲第5番 ハ短調 作品67 チェロ独奏はスロヴェニア出身のルドヴィート・カンタさん 指揮は常任の丸山嘉夫さんです。 このオーケストラについては既に色々書いているので今日はマイナス面は少なめにーみんな一生懸命弾いてるのは分かるけど、もう少し周りの音もききましょう。ホルンはもっといや、相当ガンバレ! チェロ群は少ないコントラバス群の分まで支えて大健闘していました。 また、ティンパニ奏者も存在感がありバランスよい音量でオーケストラの音色を際立たせようとしていました。 またアンコールはベートーヴェンの序曲レオノーレ!という5番シンフォニーの後のアンコールにしてはかなり難儀な曲ですが一番の熱演でした。 総督到着を告げるトランペットを舞台裏で吹かせ、2回めの時はやや近めで吹き近づいていたような立体感、ミスなく伸びやかな音でした。 あと、5番シンフォニーの終楽章の終止部でタメをつくっていて面白かったです。また、テンポもアマチュアオーケストラにしてはけっこうなもので推進力と熱気をもたらす丸山さんの指揮でした。 最後になりますがカンタさんのチェロは真っ当なきかせどころを心得ていると感じました。 ココからは今回の演奏会で一番感じたこと‼︎ 聴衆のマナーの悪さ!きっと普段音楽に触れることのない連中、というより気の回らない人ばっかし。 プログラムと一緒に大量のチラシがポリエチレンに入っていたのですがー個人的にはこのチラシ要りません!プログラム渡す時に欲しい人だけに渡すとか、出入口付近に置いておき場内アナウンスの時に案内するとか考えて欲しい。一番は音の出るポリエチレン袋はやめて下さい。自分の席の真後ろのジジイは演奏会の間ずっとパリパリ、チャリチャリ…殺意を覚えました( T_T)\(^-^ )他の奴らも演奏中にプログラム出して見るたびにカサカサ・カサカサ…殺意がふつふつと…そしてたくさんのチラシなんだから滑り落ちることくらい分かるはずなのに床にばらま